衣服の生地に使われる繊維にはさまざまなものがあり、大きくは天然繊維と化学繊維に分けられます。繊維の種類はさらに細かく分類されており、種類により性質が異なります。性質の違いを理解せず誤ったお手入れをしてしまうと、生地の傷みや型崩れの原因になるため、注意が必要です。
複数の繊維を混ぜて作られる混紡生地の場合には、それぞれの繊維の性質だけではなく、割合によっても取り扱い方が異なり、さらに注意が必要になります。そこで当記事では、混紡生地の特徴と、洗濯する際のポイントを解説します。
1.混紡とは?
混紡とは、2種類以上の異なる繊維を混ぜて糸を紡ぐことです。できあがった糸は混紡糸と呼び、生地は混紡生地(混紡織物)と呼びます。
コットン(綿)とリネン(亜麻)など天然繊維同士を混紡したり、ポリエステルとレーヨンなど、化学繊維同士を混紡したりします。また、コットンとポリエステルなど、天然繊維と化学繊維を混紡する場合もあり、組み合わせは多彩です。ここでは、混紡するメリットについて説明します。
1-1.異なる種類の繊維を混紡するメリット
異なる種類の繊維を混紡するメリットは、主に繊維の短所を補える点にあります。具体的には、下記のメリットがあります。
・生産コストを削減できる
高価な繊維の場合、安価な繊維と混ぜることでコストダウンできます。たとえば、高級繊維であるシルクは、質感の似たレーヨンと混紡することで原材料費を削減できます。
・原料不足を補える
収穫の少ない天然繊維を使用していたり、思うように原料を確保できなかったりする場合でも、ほかの繊維と混ぜて混紡すれば、不足分を補うことができます。
・紡績しやすくなる
繊維によっては、紡績しにくい性質を持つ場合があります。紡績しやすい性質の繊維と混合することで、可紡性をアップできます。
・製品の質を向上できる
異なる繊維を混ぜれば、短所を補い、製品の使用感や扱いやすさを向上させられます。たとえば、ウールは暖かい一方で、チクチクしやすい点が短所です。そこで、滑らかさが長所のカシミヤを10%程度混ぜることで、肌触りが改善されます。
混紡の効果は、繊維の組み合わせと混紡率によってコントロールが可能です。3種類以上の繊維を混紡するケースも珍しくなく、近年では混紡する繊維の種類が多様化しています。
2.混紡生地に使われる繊維の種類・特徴
混紡生地に使われる繊維の種類には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、混紡生地に使われる主な繊維の種類6つとその特徴、取り扱いの際の注意点を解説します。
混紡生地となる主な繊維には、下記のものが挙げられます。
- ・コットン
- ・シルク
- ・レーヨン
- ・ポリエステル
- ・ウール
- ・アクリル
・コットン(綿)
コットンは、「ワタ」の種子から採取される植物繊維です。生地の質感は適度なハリ感と柔らかさがあり、さらっとしています。通気性・吸水性に優れ、Tシャツやタオル、シーツなど日用品に幅広く用いられます。水や熱に強い性質があり、自宅での洗濯やアイロンがけが可能です。
一方でコットン素材には、シワが付きやすいという短所があります。乾かす際は叩いてよくシワを伸ばしましょう。
・シルク(絹)
シルクは蚕(かいこ)の繭(まゆ)から作られる天然繊維です。質感は滑らかで光沢があります。肌に優しく軽い着心地のため、肌着に用いられるほか、ドレスやスカーフ、スーツの生地にも使われます。
吸湿性と放湿性に優れ、機能性がよい反面、繊細なため取り扱いには注意が必要です。基本的には摩擦を避けて優しく手洗いするか、クリーニングを利用します。紫外線に当たると変色する性質があり、干す際は陰干しする必要があります。
・レーヨン
レーヨンは、木材パルプに含まれるセルロースを薬品で溶解して作られる再生繊維です。シルクに似せる目的で作られた素材で、光沢がありしなやかな質感が特徴です。
レーヨンは水に弱く洗濯には向きません。手洗いできる商品もありますが、ドライクリーニングが必要なケースが多くなります。シワになりやすく、熱に弱いため、アイロンがけは低温に設定し、あて布をします。
・ポリエステル
ポリエステルは、ペットボトルの原料としても知られる化学物質のポリエチレンテレフタレートを融解して作られた合成繊維です。生地は光沢のある質感で、耐久性があり、伸縮性にも優れるため、スポーツウェアによく使用されます。
ポリエステル素材は、丈夫でシワになりにくく、自宅で洗濯ができるなどメリットの多い素材である一方、静電気が発生しやすいデメリットがあります。
こちらの記事では綿とポリエステルのメリット・デメリットと、Tシャツの上手な選び方を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
・ウール
ウールは主にメリノ種の羊の毛から作られた動物繊維です。羊毛は柔らかい質感で繊維の間に空気を多く含むため、保温性があり、セーターやコート、カーペットなどに使われます。弾力がありシワになりにくい点が特徴です。
ウール素材は水に弱く、洗うとフェルト化して風合いが損なわれる可能性があります。また、虫に食われやすいため、保管する際にはクリーニングをしてから防虫剤を使用します。
・アクリル
アクリルは、石油由来のアクリロニトリルから作られる合成繊維です。ポリエステル、ナイロンとともに3大合成繊維と呼ばれます。ウールに似た風合いで柔らかく、保温性がある点が特徴です。安価で扱いやすく、虫食いもないためニットやフェイクファー、ぬいぐるみなど幅広い商品で使用されます。
アクリルは水洗いが可能です。しかし、毛玉が付きやすく、手洗いもしくは洗濯機の場合はネットに入れる必要があります。
3.混紡生地を洗濯する際のポイント
混紡生地は、複数の繊維を使用しており、単一の繊維で作られる生地よりも洗濯の際には注意が必要です。
洗濯の方法を誤るとシワができたり、縮んだりする恐れがあります。また、飲食店などの制服の場合は、シワや型崩れによってお客さんに与える印象が悪くなる可能性があります。そのため、ここで紹介するポイントを押さえて洗濯をしましょう。
3-1.洗濯表示を必ず確認する
混紡生地は、繊維の種類だけではなく割合によっても洗濯方法が変わります。洗濯する際は必ず洗濯表示のタグを確認しましょう。
2016年12月から、国際規格に合わせて洗濯表示が新しくなりました。そのため、以前の洗濯表示との違いに混乱してしまう人が多くいます。新しい洗濯表示により、洗い方が分からない場合は、下記のページを参考にしてください。消費者庁のページで、新しい洗濯表示とその意味を解説しています。
3-2.洗濯ネットを使う
混紡生地を洗濯機で洗う際には、洗濯ネットを使用しましょう。洗濯ネットは、摩擦による生地の傷みやシワ、型崩れを防ぎます。また、ほかの衣類から出たホコリや糸くずが付着せず、きれいに洗えます。洗濯ネットを使用する際のポイントは、下記の通りです。
- ・摩擦を防ぐため1枚の洗濯ネットに入れる衣類は1枚にする
- ・洗濯ネットの大きさは、シワを防ぐため衣類に合ったサイズにする
- ・衣類は畳んでから洗濯ネットに入れる
- ・デリケートな生地は目が細かく、四角い洗濯ネットを使用する
- ・汚れ落ちをアップするためには、目が荒い立体型の洗濯ネットを使用する
洗濯物を詰め込みすぎると水流を妨げ、汚れ落ちが悪くなります。洗濯機を使用する場合は、容量の7〜8割を目安にしましょう。
まとめ
混紡とは、2種類以上の異なる繊維を混ぜて紡績することを言います。混紡生地は、それぞれの繊維の種類だけではなく、割合によって取り扱い方法が異なるため、洗濯する際は洗濯表示に従いましょう。
洗濯表示は2016年12月より新しいマークに変更されています。新表示は旧表示よりも種類が増え、意味が分かりづらいものもあります。洗濯表示で分からない場合は、独断で判断せず、消費者庁のホームページなどで確認することが必要です。
また、洗濯機を使用する際には、洗濯ネットを使い、洗濯物を詰め込みすぎないことが大切です。混紡生地を正しく取り扱い、衣類をきれいに長持ちさせましょう。






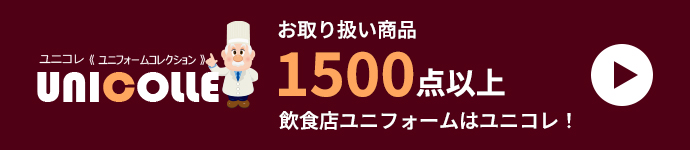







![厨房シューズ(ハイパーV)[男女兼用][住商モンブラン製品] H-5000](https://food.ths-net.com/wp-content/uploads/2022/02/51590222f379419a118b5869f22e30b4-200x200.jpg)





この記事へのコメントはありません。